
|
ここは袋井の油山寺 掛川城の大手二の門が移築されている、と言うことで先に立寄る
|
|

|
明治6年の廃藩で、太田備中守の寄進と書かれている 彼は何者か知らないが、きっと掛川城最後の城主なのだろう
|
|

|
立派な大手二の門だが、寺の山門としては似合わない
|
|

|
住職さんが門の扉は一枚板と教えてくれる
|
|

|
油山寺の弁天池 弁天とはインドの水の女神と案内あり、初めて知る
|
|

|
大きくて凄い油山寺 寺の本堂は山頂にある薬師本堂のようだ
|
|

|
麓にある宝生殿 豪華なお堂で、最初はこれが本堂と思った
|
|

|
住職さんが、横須賀城の書院も移築されていると言っていたので、見逃さずに見ることが出来た
|
|

|
まだこの辺の紅葉は早いが、一つの楓は大分赤くなっていた
|
|

|
掛川城
|
|

|
天守閣と共に掛川城の威厳を示す大手門 山内一豊が掛川城主の時代に造った
|
|

|
1993年の発掘調査で発見された大手門の礎石根固め石 セメントが無い時代に、石を固める技術があったとは驚きである
|
|

|
大手門を通ると直ぐ番所 城の出入口で不審者を厳しく見張っていたのでしょう
|
|

|
大手門と本丸の間を流れる川は、天然の外堀だったのでしょう
|
|

|
掛川城は日本100名城の一つで、城跡はとてもキレイな公園
|
|

|
本丸へ上がる手前にある三日月堀 本丸を取巻いていないが、当時もこの三日月部分だけの堀だったのか?
|
|

|
本丸への登城階段 上の門は四足門の名前で、本丸への出入口
|
|

|
掛川城の城郭図 見所が一杯で興奮する
|
|

|
この模型は間違っているのでは?二の丸と三の丸が逆のような気がしてならないが
|
|

|
油山寺に移築された大手二の丸門の扉は一枚板だったが、大手門もこの四足門の扉も一枚板でない
|
|

|
本丸の入口の左右に、立派な石垣が残っている
|
|

|
左手の石垣の上に太鼓櫓が建つ
|
|

|
本丸から天守閣を望む
|
|

|
天守閣は3階建てに見えるが、三重四階で最上階は4階になる
|
|

|
天守丸から見る本丸
|
|

|
天守丸へ上がる階段 白壁とその先の天守閣、一番絵になるポイントじゃないかと思う
|
|

|
白壁には鉄砲や弓を射る窓が等間隔に開いている
|
|

|
天守丸から見る二の丸 建屋は二の丸御殿
|
|

|
天守丸から見る四足門とその先の三の丸
|
|

|
天守下門 確かこの形の門は冠木門と言うのでは?
|
|

|
天守丸にある霧吹き井戸 1569年徳川家康に攻められたとき、この井戸から立ち込めた霧が城をつつみ攻撃から守った、という伝説があるそうだ
|
|

|
天守閣を支える石垣 天守閣が造られたのは戦国末期、野面積みじゃなくて、石を加工して積んでいる
|
|

|
天守閣は、1591年〜1596年にかけ、山内一豊が築いたとある
|
|

|
天守閣は幕末時に取壊され、1993年木造で復元された
|
|

|
天守閣の入城は410円 家康かなと思ったが一豊だった
|
|

|
天守閣の階段は狭くて急階段に決まっとる
|
|

|
鯱は金じゃない やっぱし名古屋城の方が上か?
|
|

|
天守閣の外に廻廊はなく、天守閣の窓から外を見ることに 景色は天守丸から本丸、その先は掛川市街
|
|

|
二の丸と二の丸御殿 御殿の先の森が掛川古城跡
|
|

|
掛川古城までは、歩いても直ぐのようだ
|
|

|
今川vs徳川vs武田の高天神城の争奪戦に関わった城の配置がよく分かる 今日はこの後、小笠山砦−横須賀城−高天神城を回る予定
|
|

|
腰曲輪から見上げる天守丸の石垣が凄い
|
|

|
塀と石垣の間を細長く延びる腰曲輪 景色がとっても良い
|
|

|
腰曲輪から二の丸へ出る 腰曲輪の塀の下は高い土壁で、この景色も中々見応えある
|
|

|
二の丸から仰ぐ天守閣
|
|

|
何処から見ても美しいので、つい写真撮りしてしまう
|
|

|
石垣下から見た時は白い櫓が見えなかったが、二の丸から太鼓櫓がキレイに見えた
|
|

|
二の丸御殿の玄関 天守閣の入場券で御殿も入場出来る
|
|

|
御殿と天守閣も中々絵になる
|
|

|
御殿は1861年の再建とある 幕末の動乱期に再建されたのが凄い
|
|

|
ここにも一豊が登場 一豊が掛川城主だったのは10年程だが、掛川に貢献が大だったようだ
|
|

|
調和がとれた美しい部屋並が良い
|
|

|
ちょっと殿様気分に
|
|

|
御殿の裏に大きな土塁が残っている 黒土塁の看板があったが、黒の意味が分からず
|
|

|
十露盤掘の名が付く堀 やはり当時はもっと長くて、本丸を囲っていたのでしょう
|
|

|
掛川古城
|
|

|
本丸に龍華院大猷院霊屋が建つ これは家光の霊を祀ったものとある
|
|

|
掛川古城は、文明年間(1469〜86)に駿河守護大名今川義忠が遠江支配の拠点として、重臣朝比奈泰熙に築かせた城
|
|

|
家光廟がある所が本丸で、東側に土塁が残っている
|
|

|
土塁の下は深い堀切
|
|

|
堀切に降りると堀の深さに感動
|
|

|
小笠山砦
|
|

|
小笠神社への入口を見つけるが、山の中へ入る気が起こらず 小笠山砦は高天神城を包囲する家康の砦の一つ
|
|

|
横須賀城
|
|

|
横須賀城は、家康が高天神城奪還のため、大須賀康高に築かせた城
|
|

|
本丸の南側に駐車場もありここから入城
|
|

|
横須賀城は国指定史跡で、しっかり管理されてキレイなのが良い
|
|

|
本丸南側から本丸の眺め 整然と並ぶ石垣が美しい
|
|

|
こんな丸石の石垣を見た事が無い こんな丸い石の積み上げで、よく崩れないものだと不思議
|
|

|
本丸への上り口
|
|

|
本丸は結構広い 国管理で草むらになっていないのがとっても良い
|
|

|
立派な石の城址碑があるのも良い
|
|

|
土塁もキレイに残っている
|
|

|
北の丸と松尾山
|
|
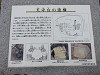
|
遺構の案内があるが、遺構そのものは良く分からない
|
|

|
本丸の下にある西の丸
|
|

|
西の丸から本丸を見る
|
|

|
西の丸から回り込んで北の丸へ入る
|
|

|
北の丸の上の松尾山へ 当初は松尾山に本丸があったと書かれている
|
|

|
本丸があったとして見ると、何となく土塁の様に見える
|
|

|
北の丸から本丸を見る
|
|

|
お姫様とあるだけで誰だか分からないが、横須賀城主の姫様を祀っているのかな
|
|

|
本丸と三の丸の間にある三日月池 水堀となっていたと思われる
|
|

|
ただ広い三の丸跡 奥の森は松尾山
|
|

|
横須賀城の不明門、大須賀康高の墓、がある撰要寺に立寄る
|
|

|
案内無いが、この門が移築された横須賀城の不明門と思われる
|
|

|
中々キレイで落着いた感じの撰要寺本堂
|
|

|
大須賀康高の墓だが、募塔が二つある
|
|

|
高天神城
|
|

|
何とも凄い高天神城の図だが、この絵は実際と合っていない
|
|

|
この絵が実際と合っていて分かり易い
|
|

|
北駐車場から搦手道で入城となる 大手道は南側になる
|
|

|
高天神城も国指定史跡で整備されているが、急坂の石段は中々キツイ
|
|

|
的場曲輪に上がる手前にある三日月井戸
|
|

|
掘った井戸でなく雨水が溜ったもの 金魚が泳いでいた
|
|

|
的場曲輪へ入る虎口?
|
|

|
的場曲輪に上がって、右方向が高天神社、左手が本丸 先ずは本丸へ行く
|
|

|
的場曲輪は鉄砲や弓の練習場
|
|

|
何者か知らないが、大河内政局石窟の案内がある
|
|

|
本丸へ上がる登城道
|
|

|
本丸には木の城址碑と看板がある
|
|

|
高くないちょっとした土塁がある
|
|
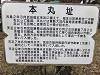
|
高天神城は、今川から家康が奪った後、信玄の攻撃は一旦防ぐが、勝頼に奪い取られ、その後再び家康が取り戻す、と言った攻防戦が行われた
|
|

|
今日は楽しい城巡りとなり、大満足である
|
|

|
石碑が無いと思ったが、ちゃんと石の城址碑もあった
|
|

|
松幹化石の案内あるが、何のことかさっぱり分からず
|
|

|
本丸下は断崖絶壁 ここから攻められる心配はないだろう
|
|

|
三の丸から本丸への虎口と思われる
|
|

|
本丸と御前曲輪の間にある元天神社 当然高天神社と関係する社だろう
|
|

|
本丸下にある御前曲輪 この顔出し撮影板は要らない
|
|

|
御前曲輪の先に三の丸があるが、御前曲輪からは見えず
|
|

|
大河内政局石窟 最後まで武田勝頼に降伏しなかった大河内源三郎政局が8年にわたって幽閉された石窟
|
|

|
家康と勝頼の因縁の戦い 凄かったのが想像できる
|
|

|
的場曲輪に戻り、高天神社へ向かう
|
|

|
鐘曲輪の看板があるが、曲輪の様子はよく見えず 削平地があり、敵が攻めて来たら、鐘や太鼓を叩いて知らせる所、と看板にあった
|
|

|
かな井戸 井戸曲輪となっている
|
|

|
高天神社へ上がる石段
|
|

|
石段を上がる手前の社務所がある辺りが西の丸
|
|

|
社務所の裏に堀切の案内あるので覗いてみると、大きな堀切が見える
|
|

|
一休みして英気を養う
|
|

|
社務所の裏から見た堀切は、神社から馬場平の間の堀切だった
|
|

|
切割と案内あるが、切割と堀切は同じなんでしょう?
|
|

|
馬場平と言うのは、言葉通り馬を繋いだ場所なんだろう 小笠山の表示があるが、山が望めないのが残念
|
|

|
社務所があった西の丸の下は、足も竦む断崖絶壁である
|
|

|
袖曲輪の案内あるが、二の丸の手前にある曲輪
|
|

|
袖曲輪の奥は、また凄い堀切 その先にも別の曲輪が続いている
|
|

|
二の丸
|
|

|
二の丸から神社本殿がある西の丸を見上げる
|
|

|
袖曲輪から堂の尾曲輪へ出た所に、本間・丸尾兄弟墓碑がある
|
|

|
本間・丸尾兄弟は堂の尾曲輪を守備していた武将で、武田の攻撃で戦死した、と標柱に書かれている
|
|

|
袖曲輪と堂の尾曲輪の間の堀切も高さが凄い
|
|

|
堂の尾曲輪間の辺りが土塁や空堀や堀切が凄いのが分かった 高天神城は北・東・南は断崖絶壁だが、西側は緩斜面であり、人工的な防衛網が必要だったようだ
|
|

|
堂の尾曲輪の長く延びる土塁と空堀 中々美しい眺めである
|
|

|
今日は高天神城の攻防戦に思いを馳せながら、素晴らしい名城を堪能でき、とっても楽しかった
|
|
|
|
|
|