
|
御嵩本陣山城
|
|

|
御嵩本陣山城は、御嵩を拠点としていた戦国武将小栗信濃守が築城した山城 御嵩城とは、この本陣山城址と権現山城址を合わせた呼称
|
|

|
山頂まで車で上がることが出来て、大きな駐車場も完備されている
|
|

|
山頂は広い削平地で、主郭部と思われるが遺構は無い ちょっとした展望塔が建っている
|
|

|
展望塔から美しい景色が望める 夜9時30分までライトアップされているようだ
|
|

|
主郭の周りに空堀らしきものが見えるが、空堀跡かどうかは分からない
|
|

|
御嵩権現山城
|
|

|
ナビは山の反対側を案内し、登城口を見つけるのに苦労したが、金峰ふれあいの森が入口で、駐車場も完備されている
|
|

|
金峰ふれあいの森の碑がある所から入ると、直ぐに大きな堀切がある
|
|

|
金峰神社へ上がる階段 かなり急だが手すりがあるので安全
|
|

|
山頂にある金峰神社だが、境内は結構広い 案内は無いが、境内が主郭部と思われる
|
|

|
階段で境内に入ったが、別な所に主郭への虎口がある
|
|

|
こちらが大手道と思われ、駐車場の奥から入れるようになっていた
|
|

|
大きな土塁も確認できる
|
|

|
堀切跡も数か所残っている
|
|

|
出丸へ上がる所にある堀切 この堀切は大きくて見応え十分
|
|

|
出丸へ上がる階段
|
|

|
出丸は結構広くて、周りにはしっかり土塁が残っている
|
|

|
次の小原城へ向かう途中、旧中山道に耳神社なるものを見つけ、ちょっと立寄る
|
|

|
耳の病にご利益があるようだが、今のところ耳は問題ないので、参拝せずに見るだけ
|
|

|
小原城
|
|

|
白山神社の奥の山が小原城跡
|
|

|
神社へは急傾斜の長い階段となるが、手すりが無いので、足腰の衰えた老人には、かなり危険と思われる
|
|

|
鳥居から100m程離れた所に、山へ上がる道があり神社へ行ける 階段より山道の方がよっぽどか安全である
|
|

|
石垣の上に建つ白山神社の本殿
|
|

|
白山神社の背後の山が城址だが、神社境内も城郭の一部のような気がする
|
|

|
山へ入るまともな道は無い 好きな人は、神社奥のこの辺りから、強引に入って行くのだろうと思う
|
|

|
和知城
|
|

|
和知城の別名は稲葉城で、天正十八年に西保城主の稲葉方通が移り築城 城跡は稲葉城公園として整備されている
|
|

|
三の丸が駐車場で、公園広場が本丸 その間にある大堀切が凄い
|
|

|
公園広場の本丸は結構広くて、異様な感じの櫓が建っているが、これは展望台
|
|

|
土塁に石垣が敷かれているが、当時の物ではなさそう
|
|

|
石垣の上に、城址の説明看板と標柱が立っている
|
|

|
大堀切に降りることが出来る 和知城の見所は、この大堀切のみのようだ
|
|

|
本丸に建つ展望台に上がると、木曽川に突き出た半島のような地形になっているのが分かる
|
|

|
展望台から本丸の眺め 本丸の奥に二の丸がある絵図になっているが、二の丸らしき曲輪跡は確認出来なかった
|
|

|
公園への入口の県道沿いに、公園案内と城址碑がある
|
|

|
金山城
|
|

|
出丸の看板は県史跡指定と書かれているが、金山城は国指定の史跡
|
|

|
中々見応えある出丸の石垣 金山城はかなり高い山城だが、出丸まで車で入ることが出来る
|
|
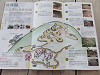
|
自由に持ち帰りできるパンフレットが置いてある
|
|

|
登城口前にある展望台からの眺望 下に蘭丸ふるさとの森が見える
|
|

|
いよいよ登城 城郭や遺構が楽しみでワクワクする
|
|

|
三の丸の入口 もっとかかると思ったが、入口から5分程で上がれる
|
|

|
二の丸西面の石垣 破城の痕跡の説明版があり、故意に壊して再び築かれないようにしている
|
|

|
金山城は古城山と言う山にあり、国有林だったのものが昭和28年に払下げられ、その記念に造られた碑とある
|
|

|
この下に湧水場があり、城内に運んだようだ 山城は何よりも水の確保が一番重要だったでしょう
|
|

|
三の丸から二の丸へ上がる虎口
|
|

|
三の丸に北曲輪の標識があり、行って見るが道は無くなり小山を直登する羽目に 危険が伴い途中で断念するが、国史跡としては有るまじき事と思う
|
|

|
三の丸から二の丸へ入る虎口
|
|

|
二の丸から三の丸を見下ろす
|
|

|
二の丸の上の本丸の土壁は、案内無いが切岸になっていると思う
|
|

|
二の丸の南端にある物見櫓跡
|
|

|
二の丸から本丸へ上がる虎口と思ったが、上がると大手桝形と案内ある曲輪
|
|

|
崩れた石垣が残る大手桝形の曲輪
|
|

|
桝形は登城する武士が、息や衣装の乱れを整える場でもあるのを知る
|
|

|
大手桝形の看板にある二の門跡
|
|

|
二の門から桝形虎口を通って本丸へ
|
|

|
桝形虎口を上がると広い削平地に出るが、ここが本丸と思ったが本丸はもう一段上になる
|
|

|
天守台西南隅石の看板あるが、天守台とあるのが今一分からない
|
|

|
天守台西南隅石の看板ある所を上がると本丸
|
|

|
金山城の攻防の歴史の看板あるが、何か読みずらい文章である
|
|

|
天守台西南隅石の看板から入った所と別な所に、本丸虎口の看板がある
|
|

|
こちらは搦手なのか? 何かよう分からなくなって来る
|
|

|
本丸に立つ金山城址の石碑
|
|

|
本丸からは展望が効き、美しい景色が気持ち良い
|
|

|
虎口から本丸を見る景色も中々良い
|
|

|
本丸の石垣 かなり崩れているが、これも破城の跡か?
|
|

|
蘭丸ふる里の森に立寄る
|
|

|
蘭丸ふる里の森から金山城を見る ここからも登城道が延びている
|
|

|
蘭丸産湯の井戸 蘭丸は金山城で生まれている
|
|

|
顔戸城
|
|

|
住宅地の中の車道沿いに、城址案内がある
|
|

|
顔戸城は応仁の乱の頃、斎藤妙椿によって築かれた
|
|

|
城址は藪の中にあるが、藪の周りに土塁と空堀が取り巻いている
|
|

|
明智長山城
|
|

|
西出丸曲輪から登城 後で分かるが、光蓮寺の所に駐車場があり、そこから大手道で登城するべきであった
|
|

|
入って直ぐに西出丸跡の碑
|
|

|
そしてすぐに本丸へ 馬防柵が出来ているが、本丸の高台には騎馬で入って来れないだろうに、と違和感を感じる
|
|

|
康永元年(1345)に美濃源氏・土岐頼兼が名字を「明智」と改めて、初代明智家棟梁となり明智庄瀬田の地に明智城を築城した
|
|

|
本丸の北端に展望台があり、素晴らしい景色を見ることが出来る
|
|

|
本丸にある明智城址碑
|
|

|
城址碑の標柱も立っている
|
|

|
七ツ塚の石碑 斎藤義竜と明智が敵対していたのが以外だった
|
|

|
大手道の道 この道の下に大手門があり、後で車で移動して見に行くことにする
|
|

|
逆茂木の石碑と木の枝があるが、何のことか理解できない
|
|

|
不可解な馬防柵だが、カッコいいので記念撮影
|
|

|
看板に台所曲輪、水の手曲輪、乾曲輪へ道が展望台から延びているが、何処にあるのか分からない
|
|

|
光蓮寺へ移動すると、大きな駐車場があり、大手道の入口になっている
|
|

|
大手門があり、ここから登城すべきだった
|
|

|
天龍寺に明智一族の墓があると言うので立寄る
|
|

|
中々感じの良い天龍寺の本堂
|
|

|
天龍寺の駐車場脇に明智氏歴代の墓所があり、小さな仏様が幾つも並んでいる
|
|
|
|
|