
|
小野城
|
|

|
林の中へは広い道があり簡単に入れる 土塁と空堀らしきものが見える
|
|

|
広い削平地は主郭部か?
|
|

|
林の左側へ行くと、大きな土塁と切通がある 全然期待していなかったが、ちょっと遺構が見れて嬉しくなる
|
|

|
ギザギザの鈴鹿山脈の山々が恰好良い
|
|

|
新所城
|
|

|
関町は、東海道五十三次の47番目の宿場町 新所城址の山へ入るのは止めて、ちょっと関宿を散策
|
|

|
関宿の西入口にある無料休憩所
|
|
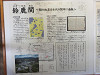
|
関の地名は古代の関所があったからとある 単純で良い
|
|

|
中々感じの良い宿場の町並み 関宿は伝統的建造物保存地区に指定されている
|
|

|
道百選の碑を見つける 日本百選巡りで道百選も巡ったので、全然記憶が無いがここも来た筈である
|
|

|
地蔵院の鐘楼の赤い屋根がカッコ良い 鐘楼は、国指定の文化財になっている
|
|

|
やっぱり新所城址の山に入ることにする 国道1号にある「長徳寺前」バス停の近くの民家から入山できる
|
|

|
入り口が分からなかったが、民家のオヤジが入口を教えてくれた
|
|

|
尾根の淵に沿って空堀が切られている
|
|

|
空堀の道をしばらく行くと行止まり 尾根を直登すれば主郭へ行けそうだが、行く気は起らず
|
|

|
正法寺山荘
|
|

|
正法寺山荘は、関氏一族の武将関盛貞によって永正(1504〜)のはじめに築かれた
|
|

|
排水溝の跡と思われる 国指定史跡なのに、遺構の案内が無い
|
|

|
山の麓の広い平地に、縦横無尽に土塁が巡らされている
|
|

|
昭和時に発掘調査が行われており、出土した住居跡に礎石が残っている
|
|

|
中々爽快な眺めだが、城郭がどうなっていたのかは、よく分からず
|
|

|
井戸跡も何カ所にある
|
|

|
山の上が主郭と思い、登城口を探すが山へ上がる道は無い
|
|

|
何とか上がれそうな所から入るが、転げ落ちそうで直ぐに止める しかしここ人が上った形跡あり
|
|

|
城郭図が何処かにある筈で、探しに再び平地を歩く 石垣で仕切られた住居跡が中々感じ良い
|
|

|
城郭図は見つからず 平地の端も土塁が巡っている
|
|

|
土塁の切通 山の上に主郭があると思ったが、平地部が主郭で、この切通は虎口では?
|
|

|
切通の下は、帯曲輪が取巻いている
|
|

|
駐車場から出ると、城郭図が描かれた看板を見つける この看板は駐車場の所に欲しい
|
|

|
関宿の道の駅で昼飯にする
|
|

|
亀山氏の歴史博物館 亀山城の散策マップを貰いに立寄る
|
|

|
折角だから博物館も見物 入館料は300円
|
|

|
亀山の戦いの説明 本能寺の変の後、賤ヶ岳の戦いが起こるが、その前哨戦が亀山の戦い
|
|

|
亀山城主は秀吉側だったが、留守の間に家来に占拠され、滝川一益に渡されてしまうが、秀吉が奪い返す戦いがあった
|
|

|
亀山城主・石川昌勝の甲冑 江戸時代の亀山城主は、徳川を出奔した石川数正の子孫がなっている
|
|

|
明治天皇と皇后、皇太子・大正天皇と皇太子妃、昭和天皇の赤ちゃんの頃、の写真があった
|
|

|
貰った亀山城の散策マップ これを見ながらじっくり巡ろうとしたが、実際はうまく回れなかった
|
|

|
広い亀山公園の中に、歴史博物館と亀山城の城郭がある
|
|

|
若山城 亀山城
|
|

|
看板と碑の後ろにある小山が若山城址 見渡したところ、小山に上がる道は無い
|
|

|
若山城は、1265年に関左近将監実忠によって築かれた 古城の名があるように、近世亀山城の以前に関氏が代々居城していた
|
|

|
亀山中学校 入手した亀山城マップに、藩校明倫舎とある
|
|

|
西出丸跡 この辺りに関見櫓跡がある筈だが、何処にあるか分らない
|
|

|
西出丸跡は、無料の駐車場になっている 歴史博物館から歩いても、10分もかからない距離
|
|

|
西出丸の北側に残る大きな土塁
|
|

|
亀山神社 後になって神社境内が本丸だったと気付く
|
|

|
大久保神官家棟門の標柱があるが、亀山城との関係が全然分からず
|
|

|
亀山神社の境内が本丸なのに、本丸の案内は無い この後、本丸を探して神社周りを、うろうろすることになる
|
|

|
亀山神社の対面にますみ児童園があり、ここも含めて本丸跡と思われる
|
|

|
亀山城は、1265年関実忠によって築かれた亀山古城がその始まり 近世の亀山城が築かれたのは1590年に亀山城主となった岡本下野守宗憲の時で、この時に天守が造られた
|
|

|
亀山神社の隣りにある多聞櫓
|
|

|
多聞櫓の中へは自由に入場できる
|
|

|
多聞櫓内部
|
|

|
多聞櫓は見事な石垣の上にあり、ここが天守台跡であるのを後で知る
|
|

|
明治天皇行在所 明治13年に天皇は三重県を巡幸した旨の看板があり
|
|

|
ますみ児童園の北側に三重櫓跡がある
|
|

|
標柱に、1641年に天守閣の代わりとして築かれたとあり、ここに三重の立派な櫓があったようだ
|
|

|
ますみ児童園の北側にある水堀跡の池
|
|

|
二の丸帯曲輪へ行こうとしたが、池回りでは曲輪へ行けなかった
|
|

|
高台に、亀山小学校と帯曲輪跡が見えるが、ここからは帯曲輪へ上がれず、ますみ児童園に戻ることに
|
|

|
二の丸はとても広かったようだ 小学校から隣の市役所の広大な範囲が二の丸跡
|
|

|
埋門の案内 帯曲輪と二の丸御殿の間に造られた門とある
|
|

|
石垣造りの小さな門だが、中々感じ良い
|
|

|
二の丸の下に広がる帯曲輪 塀に鉄砲や弓を打つ小窓が無いのが不思議
|
|

|
石積みの一部が残っている 帯曲輪と二の丸の壁は石垣があったようだ
|
|

|
帯曲輪から見る埋門 中々恰好良い
|
|

|
多聞櫓の車道沿いの所に城址碑がある
|
|

|
多聞櫓の東側から見ると、凄い石垣に圧巻される
|
|

|
この石垣で、多聞櫓の所が天守台であるのに気付く
|
|

|
二の丸の東にある東三の丸へ行こうとするが、道路工事中で入れず
|
|

|
阿野田城
|
|

|
阿野田城は連光寺北側の森の中 連光寺への坂道の両側は、見事な石垣が並ぶ 中々見応えある景色
|
|

|
立派な連光寺の山門 上は鐘楼になっている
|
|

|
連光寺の隣の民家の奥の林に、はっきりとした土塁が残っていた
|
|
|
|
|