
|
市場城(再訪)
|
|

|
文亀2年(1502年)鈴木親信によって築かれた 鈴木氏は市場古城を居城としていたが、親信の時代に市場城を築き居城を移した 天正11年(1583年)4代・重愛は徳川家康に従って串原・広瀬の城を攻めて功を挙げ、領の加増を受けて城を改修した
|
|

|
市場城の駐車場 トイレはウォシュレット
|
|

|
駐車場の対面の山が城跡で、登城口に案内看板ある
|
|

|
コンクリートの登城道を上がると直ぐに城跡
|
|

|
見所が沢山ある 右回り:順路で巡る
|
|

|
赤い鳥居の所に城主の供養塔の案内あり
|
|

|
初代・紀伊守親信、二代・肥後守長重、三代・伊賀守直重、四代・越中守重愛、の供養塔
|
|

|
これが供養塔と思われるが、刻まれている文字は殆ど読めない
|
|

|
空堀の案内 景観がとっても良い
|
|

|
この空堀は二の丸西側に位置する 右側の高くなっている所が二の丸
|
|

|
櫓の石垣の案内 中世の山城の石垣は数少なく貴重と書かれている
|
|

|
野面積の石垣
|
|

|
櫓の石垣と案内あるので、石垣の上には大きな櫓があったのでしょう
|
|

|
櫓台から下の空堀跡を見る
|
|

|
櫓台は本丸を取巻く帯曲輪になっている
|
|

|
本丸の石垣も見事
|
|

|
本丸の南に位置する二の丸 小原は四季桜と紅葉が名所 二の丸広場は四季桜林になっている
|
|

|
二の丸から本丸への登城道 中々美しく感動する景色
|
|

|
本丸にある城址案内
|
|

|
本丸は2つに分かれていて、こちらは北側の本丸跡
|
|

|
石の城址碑とちょっと紅葉が始まった木
|
|

|
こちらは南側の本丸跡 さすが豊田市草刈がされているのが助かる
|
|

|
南の本丸の周りには土塁が残っている
|
|

|
南端から下の櫓台を覗く
|
|

|
東側は自然の急斜面
|
|

|
本丸の北端 下は帯曲輪が取巻いている
|
|

|
これは猪のしわざと思う
|
|

|
北側の本丸から西下の曲輪へ下りる
|
|
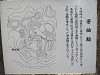
|
馬蹄型の3段の帯曲輪の案内
|
|

|
案内にあるような3段の帯曲輪に見えない
|
|

|
3段の帯曲輪から下の曲輪へ
|
|

|
竪堀群の案内
|
|

|
竪堀群は愛知県下で唯一の確認例とある
|
|

|
大きな竪堀が確認できる
|
|

|
横から見ると幾つもの竪堀が切られているのが分かる
|
|

|
竪堀群を奥へ入ると、北側本丸と曲輪の間の大堀切がある この堀切は中々凄い
|
|

|
堀切の奥は竪堀が谷へ落ちている
|
|

|
竪堀群を南側から眺める 市場城の一番の見所は、この竪堀群と思う
|
|

|
桝形門の案内
|
|

|
桝形虎口の石垣
|
|

|
石垣に続いて尾根の堀切 この景色も素晴らしい
|
|

|
桝形門を出た所はさんざ畑 尾形三左衛門屋敷跡と書かれている
|
|

|
さんざ畑から桝形門の大堀切を見る
|
|

|
さんざ畑の東下の広い削平地は家臣の屋敷跡 市場城は再度の訪問だが、素晴らしく大変感動した
|
|

|
市場古城(再訪)
|
|

|
熊野神社の奥の森が城郭の東端 鳥居の横の大杉は、豊田市の文化財と案内ある
|
|

|
急階段だが手すりがあるので何とか上がれる
|
|

|
熊野神社本殿へ上がる山道
|
|

|
熊野神社西側の堀切
|
|

|
熊野神社本殿の周りは高い土塁 狭い本殿境内は、城郭の東端の曲輪跡と思える
|
|

|
城址の案内は無いし、整備された道も無い 本殿裏から堀切の尾根をよじ登る
|
|

|
大きな土塁と思うが、藪の中で気分は今一
|
|

|
土塁の下に削平地が広がり小さな社がある
|
|

|
削平地の奥に大きな堀切があり、その先が主郭へ続くと思われるが、道が無いので此処までとする
|
|

|
市場古城の築城年代は不明 応永年間(1394〜1427)には鈴木重勝が居城していた、とネットある
|
|

|
市場古城も市場城同様に整備し、両城セットにして宣伝すれば大勢の城ファンが訪れると思うのだが
|
|

|
川口城(再訪)
|
|

|
天神社の裏山・城ヶ峰が城跡で、天神社境内に、城址への登り口の案内ある
|
|

|
距離は短いが、かなり急傾斜の石段で結構疲れる 頂上まで10分かかった
|
|

|
主郭下の曲輪 主郭を取り巻く帯曲輪になっている
|
|

|
曲輪の先にある堀切 小さな堀切で案内無いと見落とすだろう
|
|

|
更に先に、もう一つ小さな堀切
|
|

|
主郭への上がり階段
|
|

|
狭い主郭に、休憩所があり川口城址の看板
|
|

|
室町時代の城主は水野正春次 1575年武田軍の三河侵攻により落城
|
|

|
ここは西三河の山間部 遠くに矢作川が見える
|
|

|
主郭から下の帯曲輪の堀切
|
|

|
天神社の対面にある水汲遺跡
|
|

|
縄文遺跡で、この辺りには一万年前から人が住んでいた
|
|

|
御作城(再訪)
|
|

|
天徳寺の裏山が御作城跡
|
|

|
天徳寺の境内から登城道が延びている
|
|

|
御作城は鎌倉時代の砦と案内ある 築城時期や築城者は不明のようだ
|
|

|
かなり長そうな登城道だが、10〜15分の案内ある 登城道には檀家の33の観音堂がある
|
|

|
一番目の観音堂
|
|

|
暫く登ると見晴台に出る
|
|

|
峠を登ると道は下がり、ここが堀切跡と思える
|
|

|
堀切の両側は自然の傾斜が谷へ落ちている
|
|

|
主郭手前の曲輪に31番目の観音堂
|
|

|
城址の碑でなく展望台の碑
|
|

|
狭い主郭に建つ展望台
|
|

|
展望台からの眺め 左が猿投山で右が三国山
|
|

|
豊田市市街は遠すぎてキレイに見えず
|
|

|
展望台から狭い主郭部を写す
|
|

|
西広瀬城(再訪)
|
|

|
この看板は実際と違う、と通りすがった爺さんが言う
|
|

|
矢作川の西側で、織田氏の蒋・佐久間氏が居城 矢作川の東の三宅氏の広瀬城に対抗して築かれた
|
|

|
折角だからちょっと草むらの登城道へ入ると、何とらしく堀切のような
所
|
|

|
草むらの削平地は曲輪跡と思われる もうヘビはいないだろうから、草むらを掻き分けて中へ
|
|

|
城跡の山は荒れた竹藪
|
|

|
曲輪か堀の様に見えるが、藪が酷すぎて退散
|
|

|
入るんじゃなかったと大いに反省 この張り付いた草の種、払っただけじゃ取れない
|
|

|
矢作川越しに西広瀬城跡の山を見る 手前の森の奥の山が城跡
|
|

|
矢作川の東側の東広瀬城跡の山
|
|

|
東広瀬城(再訪)
|
|

|
城址の南側の県道から登城出来る 土塁の登城道から広瀬神社の鳥居をくぐる
|
|

|
登城道は主郭下の帯曲輪 右の高台が主郭部
|
|

|
広瀬城址の看板 小屋がある所は主郭下の曲輪
|
|

|
興国五年(1344年)に児島高徳が築城 三宅高清(児島氏11代)が織田氏に属したため、永禄三年(1560年)に松平元康に攻められ落城
|
|

|
主郭への上り 神社の階段の横には登城道もあり
|
|

|
主郭には広瀬神社本殿が建つ
|
|

|
広瀬城址の立派な石碑もある
|
|

|
当時の登城道・虎口跡か?
|
|

|
山神の石造に蝶々が
|
|

|
色鮮やかな蝶々 何て名なんだろう
|
|

|
車で入る時気付かなかったが、県道沿いに東広瀬城址の石碑がある
|
|

|
城主の三宅氏は、松平から織田へ寝返ったので家康に討れた 1560年と言えば家康は10代の若造だが、さすが天下取りの家康強かったんだ この後、西三河も直ぐに平定している
|
|